“内閣総理大臣臨時代理”という職務があることを、
私は学部の学生のころ初めて知った。
1980年に行なわれた衆参同日選挙、大平正芳首相が遊説中に倒れ、
そのまま亡くなるということが起きたが、
その際、総理大臣臨時代理を務めたのが、内閣官房長官であった伊東正義であった。
伊東は総理大臣の代理なのであるから、首相執務室に入るのが当然であったが、
決してそうしようとせず、また、閣議においても首相の席には座らなかった。
その後、大平の後継は派閥内ナンバー2であった鈴木善幸と決まったが、
後に“暗愚の帝王”と呼ばれるようになる鈴木は1981年、
“軍事同盟”という言葉の響きに恐れをなし、
「日米同盟は軍事同盟ではない」と発言する。
日米同盟には当然、軍事同盟の意味合いが含まれているとして、
伊東は即刻、外相を辞任した。
1989年、リクルート事件と消費税の不評により竹下内閣が退陣すると、
金権腐敗とは無縁であった伊東が党を挙げて総理・総裁に乞われたが、
彼は頑なにこれを固辞しようとした。
あらゆる政治家は、その才能の有無、人徳の有無に関わらず、
最高権力者の座に就きたがる。
莫大な金をつぎ込み、人を裏切ってでも、そうしたくなるという。
伊東のような見識と、骨のある政治家はそういるものではないと思っていた私は、
きわめて興味深くことの経緯を注視していたが、
伊東がこれを受諾することは遂になかった。その際、彼は、
「本の表紙を変えても、中身を変えなければ駄目だ」という名言を残している。
もしあのとき、伊東が総理・総裁の座に就いていたらどうなっていただろうか……
当時、伊東は糖尿病に苦しんでいた。
したがって、家族は彼が総理大臣になることに、真に反対したという。
また、表紙だけ変わっても中身の変わらぬ自民党が、
そのまま改心したとももちろん思えない。
伊東が改革を断行しようとしても、守旧派はそれを許さなかっただろう。
それでも、政治家となった以上、たとえ自らの身が滅んでも、
改革を断行することはできなかったのか……。
仕事でたまに福島県を訪れることのある私は、
会津の生んだ希代の政治家「伊東正義」を思うとき、
今もそんなふうに考えてしまうのである。


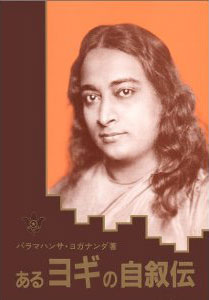
先ごろ山本太郎議員が国会で明らかにしたように、日本国憲法の上位に米国との協定や密約が存在する日本の政治は民主政治ではなく、属国政治と呼ばれるべき代物です。自民党は能動的にこの属国状態を維持することで政権基盤を堅固にしてきた政党であり、対米従属路線を覆そう、米国の裏をかこうと試みた政治家は押し並べてよからぬ末路を辿ってきたわけです。
それは官僚や著明な言論人の中に米国側のエージェントが多数潜んでいるからかもしれず、件の法案もまた、何をどう騒いでデモを試みたところで既定路線ではないでしょうか。
そこには既に70年の歴史があり、もはや誰か一人の偉大な政治家の登場だけでどうこうなる状態ではないし、誰か一人の政治家が悪いというわけでもないのでしょう。
米国の悪事の片棒を担いでいる限り、個人も組織も国も経済的な繁栄だけは約束されるというこの構造。実際、他国の例に見る通り、国防を本気で、しかも自力でやるとなるとお高くついて、国民負担は計り知れません。
・・・のような政治色の強いコメントはここではご法度でしたかね(苦笑)。