小泉は組閣にあたり、派閥の推薦を受け付けなかった。
閣僚・党人事を総理・総裁が自分で決めるということは、制度上は当たり前のことだが、
しかしそれは実際のところ、政治的な天才・小泉にしかできないことだった。
つまりそれほど、日本の政界は派閥でがんじがらめだったのである。
弱小派閥の領収であった盟友・山崎拓を幹事長に起用する一方、
最大派閥・橋本派からは党三役を起用しないという、
これも当時では考えられない“離れ業”である。
民間からは竹中平蔵を経済財政政策担当大臣に起用し、
慎太郎の息子・石原伸晃を行政改革担当大臣、
5人の女性を閣僚に任命したが、
そのうちの一人は、論功行賞による田中眞紀子(外務大臣)であった。
小泉は当初、田中には文部大臣のポストで報いるつもりであったが、
田中がそれでは納得しなかったのである。
一般に、この世界では、「ポストが人を造る」といわれる。
最初は力不足と思われても、そのポストについて精進・研鑽を積むならば
それなりに格好がついていき、人間も育っていくという意味である。
しかし田中眞紀子の場合、そのような法則性をはるかに超えた人材だったらしく、
就任後は終始小泉を悩ませ、足を引っ張ることとなる。
はるか後、自民党を離党した田中は民主党政権下で文部科学大臣となるが……
そのときも大騒動を繰り返した。
一人の人間として、外からみている分にはとても面白い人だと私は思うのだが、
政治家としてはいかなるポストにも向かないことを、自ら証明してみせた形となった。


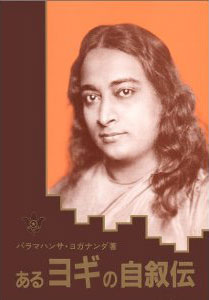
マハーバーラタを読んでみた。
ギーターが語られた後、壮絶にして悲惨な、そして信じ難くも美しさをも併せ持つ大戦争が行われる。それに勝利した5兄弟の長兄ユディシティラは、体中ハリネズミのように矢が刺さり死を迎えようとしている、敵方にいた大伯父ビーシュマに、国家運営ついて教えを乞う展開となる。
やるべき事、やってはならない事、注意深くあらねばならない事など様々に具体的に詳細に語られる。その内容は人事、内政、外交、国防、祭祀など必要十分な分野に渡る。現在の日本や日本を取り巻く国際社会に照らし合わせて、様々な気づきが与えられている。
戦争に反対するのは簡単であるが、平和を築き維持することが如何に難しいかがビーシュマの教えから学び取れる。相対界の複雑さからすれば、戦争反対と叫ぶことが平和を脅かすことすら有り得ると心得、注意深くあらねばならないと感じる。
宇宙真理の一旦を発見した名だたる科学者たちの多くがヴェーダを熱心に研究していたと聞く。生命活動の全てが科学であるならば、国家運営を扱う政治の世界も科学されるべきであり、少なくともリーダーとなる人はマハーバーラタを学ぶ心を持っている人であってほしいと思う。
巷には、この竹中平蔵氏こそ、米国側のエージェントで日本植民地化の功労者だという見方が根強くあります。それが根も葉もない陰謀論であるかどうかは各自の判断に委ねるしかありませんが、戦後から始まった能動的隷属の歴史を鑑みるに、さもありなんと思わせる根拠には事欠きません。
歴史的にみて、まず法律を自分たちに都合よくこしらえた上で、その悪法に則って相手の富を簒奪していくのが欧米人の常套手段です。彼らにとって、支配者とは文字通りruler。
システム(=法)を構築した者が勝者で、そこでのプレイヤーは決して勝者にはなれないということを彼らは熟知している(カジノがその好例)。
となれば、彼らにとって、敵国の立法府にエージェントを送り込むのは実に合理的な戦術といえるでしょう。
実際、同盟国とはいいながら、米国にとって、依然として日本は仮想敵国であり続けているのかも知れません。米軍は時々、日本の原発を標的とした軍事訓練を行っているという指摘があり、実際に伊方原発のすぐ傍で米軍機の墜落事故が起きているのですから・・・
先生のブログのショートカットのアイコンをパソコンやタブレットのホーム画面に出し
来る日も来る日も
(クリック) 大ホーマ
(クリック) 大ホーマ
の日々をを繰り返してきました。
9月6日になったらSHOさんにならい
”むむむ・・・これで放置プレイも1年をを更新か・・・。”
とコメントしようと密かにたくらみ、先生にはいろいろ事情があるでしょうから
「ブログ更新してください」などど、先生に絶対に言わないと
逆放置プレイを決め込んでおりました。
先生の文章の表現、大好きです。